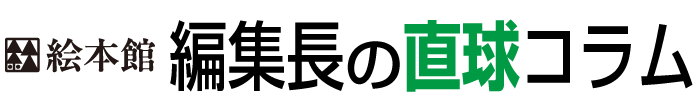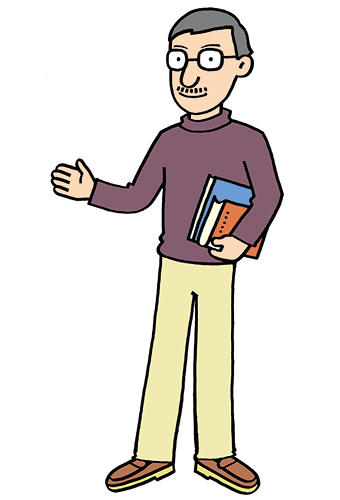 マスコミで頻繁に使われているので、われわれも日常あまり気にしていませんが、どこかシックリしない、なんだか変だなという言いかたがあります。
マスコミで頻繁に使われているので、われわれも日常あまり気にしていませんが、どこかシックリしない、なんだか変だなという言いかたがあります。
「おやじがり」
主語は加害者です。
加害者が主人公では被害者はキツネやウサギのような存在になってしまいます。
加害者は犯罪者だし、行為は強盗です。
結果次第では殺人です。
それなのに「おやじがり」では、ヨーロッパの王侯貴族が馬に乗り、おもしろがって獲物を求めて走りまわる。
そんなイメージがあるために、ことの本質を曖昧にしてしまっているのではないでしょうか。
「いじめ」
いじめっ子とは、弱い子どもをいじめてよろこぶわんぱくなガキのことです。
「いじめ」もおさない子どもたちのあどけない一種のあそび、そのようなことばにもきこえます。
ところがいま問題になっている「いじめ」はむかしのいじめとはレベルのちがうものです。
一対一ではなくて個人対集団の恐喝や脅迫です。
いじめということばが「おまえたちは卑劣な人間なんだぞ」という強い叱責の声を曖昧にさせているのではないでしょうか。
「読みきかせ」
言いきかせる、という言葉があります。
悪いことをした子どもによく分るように教えきかせる、ということです。
「読みきかせ」ということばのニュアンスも、いやがる子どもを無理やり押さえこみ、きかせるというイメージが、ぼくには浮かんできます。
「子どもに絵本を読む」でどうでしょう。
長ったらしい言いかたですが曖昧ないいかたではありません。
なんでも短ければいいというものではないのです。
長くて、もたもたした言いまわしを一機に短く、そして適切な表現をみつけだすことが文学者のおおきな仕事だし、社会への最大の貢献です。
だから「読みきかせ」にかわるべきことばが発見されるまでゆっくりまてばいいのです。
強盗などと考えもせずに、「おやじがり」なんだからと、ちょっとした遊び程度の気持ちでやったことがじつは重犯罪。
はじめはからかい程度の気持ちだったし、オレはたいして「いじめ」たつもりはなかったのに、相手は自殺。
状況を認識する力のなさが原因です。
個人対複数。いずれにしても卑怯です。
集団のなかにいるとほとんどなにも考えなくなってしまうのです。
学校でも会社でも暴力団でもサークルでも、集団のなかに長くいると個人はだんだん鈍くなり、鈍感になるのではないでしょうか。
組織に属する人が増えれば増えるほど、情報は山のようにあるのに、考える人は少なくなっていきます。
これが来たるべき情報社会の見取り図のようなきがします。
子どもたちがことばを曖昧に受けとると、将来の社会はノッペリとしたものになるのではないでしょうか。
だからことばにたいする個人の感受性は社会にとっても大切です。
絵本はどんなことができるのか、「絵本ガイドII」にヒントのようなものをみつけてくださればさいわいです。