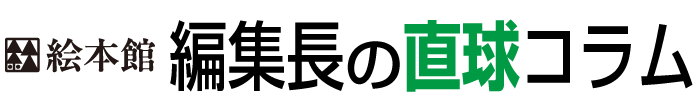選択とは、そのこと自体が知的行為である。(桑原武夫)
ぼくにとって「目から鱗」というか金言です。
自分自身の「選択の歴史」を振り返ってみると暗黒の時代というものがあった。小中高校です。学校にあるのは横並び。生徒たちに選択させる、という考えはどこにもない。唯一の選択はクラブ活動を選ぶことぐらい。
桑原さんの金言が真実に近いとすると、学校は子どもに知識を注入することには熱心だが、結果としては知性とは縁のない大人を大量に生みだす装置になっているのではないか。皮肉なことです。(あるいは為政者の目論見どおりか)
これを裏付ける言葉があります。
受験のための勉強は、教わったとおりに丸暗記するだけ、習ったこと、暗記したことを素直に信じ込める人が有利です。彼らは現実に照らして考え直すようなことはせず、生身の現実を前にすると思考停止する。(藻谷浩介)
試験は過去の学習に対する評価、未来とは直接関係しない。計画や企画一般は未来に属する。偏差値の高かった軍人、官僚、電力会社役員の思考停止はこの百年いやっというほど経験している。にも拘わらず、多くの人々もマスコミも試験の成績が優秀な人間は将来にたいしても有能な力をもっていると漠然とおもっている。しかしそういった構造は明治以降いまだにゆるがずにきている。
思考停止にならず、自分の判断で選ぶ。その選択の腕を上げるのに格好の場所は自然。その自然のなかで遊ぶことでおもわぬ力をついてくる。その次が書店ではないかとおもう。それも子どもにとっては身近にある町の本屋。
自身小学校の高学年になって町の本屋に行くようになった。それも一人で行く。悩みに悩んで一冊買う。「なぜこんな本を買ってしまったのか」の連続だった。たまにしか「これは」という本には出会わない。確率はすこぶる悪い。そのうえ父には「お前のはただのつんどく主義だな」と笑われる始末。しかしその度重なる失敗が財産になっていた。とぼしい小遣いで本を買ったうえに失敗するのだから、身にしみないわけがない。
つまり町の本屋は、子どもが本好きな大人になるための「ゆりかご」の役割を果していた。そのうえ、あらゆる趣味は身銭をきってこそ手があがる。読書が趣味になったのも地元の書店のお陰だとおもう。
大型書店やネット販売の底辺をささえてきたのも実は町の本屋の存在だということを忘れてはならない。町の本屋の減少は業界全体にとって由々しき事態です。ことは業界だけではない。
大人たちがしっかりと知性と教養を持ち判断ができる人になれる。(山田桂一郎)
か否かは日本の社会にとっても由々しき問題だとおもう。
最後にもう一つの金言。
読んでおもしろかった本が並んでいる本棚は「精神のアルバム」(林望)のようなもの、だそうです。林さんは図書館で借りておもしろかった本も、わざわざ買って自分の本棚にならべるとのこと。子どもや孫がよろこんで読んだ本、おもしろかった本だけがならんでいる本棚。そんな本棚は見ているだけでうれしく心なごむものでしょう。