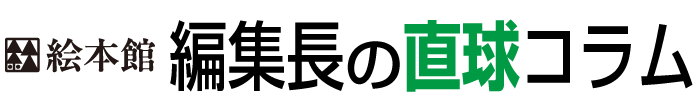幼児教育に5領域というものがある。
人間関係、環境、言葉、健康、表現の5つ。子どもの行動、生活を5つのジャンルに分ける。つまり分類する。
なんでも分類する。これが近代の悪いクセではないか、とおもうことがある。それにしても人類が分類というものを考えだしたのはいつのころなのか。
分類とか、仕分けをしていけば、問題の核心に到達できるという考え方。
たしかに科学は、そういう手法で進歩、発展してきた。それは事実だとおもう。
分けて分けて原因を究明すれば問題の解決に近づく。結果にはかならず原因があると考え、問題の原因と結果のあいだに一定の関係をみいだす。これを因果律という。
「こんな悪い結果になった原因はこれだ」とか、「このやり方で一生懸命はげんだらすごく良い結果になった」というもの。すぐにおもいあたるのが、受験やダイエット、病気など。「なにが癌の原因か」といった考え方。
科学はこれでやってきた。だから、なにごともこの考え方でやってみたくなるのも人情といえば人情であろう。
ところが、この因果律がすべてに有効かというと、そうともいえない分野もある。
究明すれば原因がわかるジャンルと、因果律で考えてもどうしてもわからないジャンルがある。勿論わかる代表は科学、わからないジャンルの最たるものが人間の心。
恋愛を因果律で考えて得るものがあるだろうか。男女の生活と行動を5つの領域に分けて、恋愛を考えてみる。
そんなことをしてもなんにもならない。
若い男女で無理なことを幼児ならだいじょうぶとおもう根拠はなんだろう。
大人は複雑、幼児は単純だということか。
以前、河合隼雄さんにお会いしたとき
心理学をやっている私は、他人の心を見通せる力を持っている。そうおもう人がいる。だから私と話すのをこわがる。ところが私たち心理療法士は、人の心のうちはよくわからないということをよく承知している。だからこそこの仕事ができる。人の心はわからない。それに心は人それぞれ異なる。だから相談に来る人の話をただただよく聞く。答えも指示もなにもしない。ただ聞く。すると話している人が自分の意識の下にかくれていた自分にだんだん気づく光がさしてくる。
と、話してくださった。
人間は、論理的に理路整然と説得され、そのうえなるほどとおもっていても真から納得しない。そんな生きものなのでしょう。だからなにかにつけストーリーが必要になる。
自分の力で気づく。そこが肝心要。
教育の要諦も本当はここにある。子どもみずから気づく。それまで大人はまつしかない。
大人になるということは、世の常識を身につけることでもある。社会の規範を身につけ、その社会がもとめている形に向かっていくのが大人。
ところが、子どもはむかしから「7歳までは神のうち」などと言う。7歳までの子どもはまだ完全に人間の仲間入りをしていない。まだ神の領域にいる。むかしの人はそう考えた。子どもは常識や因果律でものを考えるクセが身についていない。だから大人から見ると平気でわけのわからないことをやる。
むかしの人は、自分たちが理解できないものや現象は敬うことで対処してきた。子どもはわからないところがある。だから「7歳までは神のうち」といったのではないか。子どもは毎日、神の世界に行ったり、人間の方にやってきたり、そんな生活をむかしも今もおくっているのだとおもう。
人間の子であったり神の子であったり、そんな子どもたちが読んでいる絵本のことを考えてみる。ここでいう絵本とは、絵を使って子どもがわからない言葉や文章の手助けをする。そんなむかしながらのさし絵のような絵本のはなしではない。
 長新太さんの絵本。多くの大人たちは「いったい、この作者はなにをいいたいのですか」とおもう。たとえば『ごろごろにゃーん』(福音館)。
長新太さんの絵本。多くの大人たちは「いったい、この作者はなにをいいたいのですか」とおもう。たとえば『ごろごろにゃーん』(福音館)。
大人は「この絵本、最初から最後までごろごろにゃーんだけど、作者はいったいなにをいいたいのでしょう」と、そういう印象をもつ。
起承転結もなければ因果もない。もちろん子どもを導こうという気もなければ、子どもになにかを教えようという気もない。ただただ「ごろごろにゃーん」なのである。
大人はなにがいいたいのかわからない。だから当然大人には人気はでない。ところが子どもたちには人気がある。
なぜか。こういった世界を子どもは日常感じている。なにしろ子どもはわか
るわからないでは生きていない。
五味太郎さんの『のでのでので』(絵本館)も同じ。
前にあったことが原因で次のことが起こった場合。その説明のために「ので」とか「だから」がある。それが普通。ところが、この絵本の「ので」は、そうではない。因果律の上に立っていない。というより、因果律にそむいている。にもかかわらず絵本としてはなんの違和感もない。それどころか、絵本だけがあらわせる確たる世界をもっている。
因果律が通用する世界と通用しない世界がある。その因果律が通用しない世界を表現したら絵本の右にでるものはない。このフィールドは子どもにとってなじみの世界。子どもがよろこぶのはあたりまえ。
絵本は因果律からすこし離れた空間を自由自在に浮遊できるほとんど唯一のジャンルではないか。絵画、小説、映画などではいいあらわすことができない世界を絵本作家はいともたやすく表現できる。
動物やお化けなど、ありとあらゆるものに共感する力を子どもはもっている。人間としてはまれな、というか特別な能力をもっている。そんな子どもたちが読者だから、あたりまえといえばあたりまえ。作家が「あなたはなにをいいたいのですか」絵本を出版しても、子どもは平気でうけいれる。これが大きい。
神も鬼も妖怪もお化けも、石でも風でも木でも、ありとあらゆるものが出はいり自由。そんな絵本だからこそ、大人のもつ因果律など意に介さない。
絵本の絵と文のコンビネーションがうまくいくと、つまり「あなたはなにをいいたいのですか」絵本のことです。
すると、今までわれわれが大人になってから味わったことのない世界を見ることになる。古今の言葉使いの名人、達人でも言いあらわすことができなかった領域。子どもなら、いくらか感じていた世界。そんな微妙なところを、絵本はいともたやすくいいあらわすことができる。
それに、この絵本から見えてくるものは多様で広い。たくさんの魅力、醍醐味がかくされている。この魅力や醍醐味に自分の力で気づく。そうなると絵本をたのしむレベルがまったくちがったものになる。別の言い方をすれば、読むたびにあらたな発見がある。それがこの絵本の最大の特徴です。想像力の入口はここにある。
なにより子どもにとって、神の世界に行ったり人間の方に来たり、そんな生活の実感に一番近い絵本が、この絵本なのだとおもう。
作者がなにをいいたいのか、大人にはさっぱりわからない絵本。そんな絵本のおもいでがある。
長新太さんの『ぼうし』(文化出版局)。
この『ぼうし』の最後のページの「ちょうどいい」という文、これがわからない。2匹のさるが一つのぼうしをかぶっている。どう見てもちょうどよくない。そうとしか思えない。それなのに文は「ちょうどいい」となっている。
30年程前、五味太郎さんがこの絵本を見ながら、「おかしいよなあ、ちょうどよくないんだけど、いいんだよなあ」と、うれしそうにこのさるの画面を見せてくれたことをおもいだす。
その時、ぼくは『ぼうし』という絵本を見ても、その面白さがわからなかった。音楽でも絵本でも、わかるわからないと考えるとろくなことがありません。言いなおします。感じいることがなかった。ただキョトンとするばかり。
なにしろ、当時のぼくは、すべては因果律で割り切れるとおもっているドン・キホーテのような男だった。だから、この絵本の微妙な感じを受け入れるような心のもちあわせがなかった。
どこが「ちょうどいい」のか、さっぱり見当がつかなかった。
人間大人になるにしたがってわかるわからないという理の世界で生きていく。「ちょうどよくないんだけど、いいんだよなあ」という気分にはなかなかなれない。なるためにはものを見る目、人を見る心にゆとり、余裕が必要。反転して考えてみれば、この「あなたはなにをいいたいのですか」絵本は心にゆとりや余裕をはぐくむ力をもっているのかもしれない。
それにしても、自分自身いつからこの「あなたはなにをいいたいのですか」絵本をたのしめるようになったのか。進歩したのか、子どもにあともどりしたのか、わかりません。わかろうとするより、この絵本をただただ愉しめるようになった今の自分をまんざらでもないとおもっています。
大人のあなたでも、こんな絵本にであったら、そのときはチャンスです。おそくはない。絵本の世界が広がります。
ぜひ「あなたはなにをいいたいのですか」絵本を手にとってみてください。
永くねむっていた自分に気づくかもしれません。