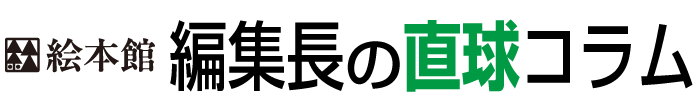学校信仰というものは明治時代に生まれた。
ところが博物学の南方熊楠さん、書と料理の北大路魯山人さん、作曲の武満徹さん、建築の安藤忠雄さんなど独創的な仕事をした人は独学の人に多い。
小説家はみな独学。小説講座に通って文豪になった人はいない。絵かきでも中川一政さんや山下清さんなど独学の人はいくらもいる。ことに山下清さんなど偏差値は低いほう。そのほうが絵の世界では有力な人になれるのではないかとおもってしまう。
工芸や職人の世界でも、親方は弟子に手とり足とりどころかなにもおしえない。ただ近くで見る権利だけをあたえる。ここでもあるのは独学。
芸術、文芸の世界だけではない。実業の世界も、ことに創業者は松下幸之助さん、本田宗一郎さんなど、偏差値や学歴などまるで問題にしない。
どういうことなのか。学校教育を受けないほうがいいのか。もちろん有力な仕事をした人でも大学を出た人はいる。たとえば戦後最大の独創的な経営者の一人が宅急便をはじめたヤマト運輸の小倉昌男さん。ちなみに小倉さんは東大の経済学部。
にもかかわらず独学のもつ力はすてがたい。独学のメリットは一人で模索するところにある。決められたレールの上を歩くのではなく、一人でやっていかねばならない。当然混乱する。その混乱が実はエネルギーとなる。どんなエネルギーかというと疑問から生まれるエネルギー。
混乱が、考えるエネルギーの元になっている。考えるとは「どうしてだろう」という疑問をもつ力ではないか。そのためには日常自然に疑問がわきでてくるような頭にしておかなければならない。自分なりの問いや疑問があればこそはじめて答えを得たいという気持もおこる。ここが考える人のスタート。
「なぜだろう」「どうして」という疑問、混乱こそが子どもにかぎらず人間の能力を伸ばす最も有効な手段なのではないか。明治以降、学校教育はここに意を注ぐことがなかった。あったのは効率だけ。
学校教育では、混乱しているひまはない。ゆっくり混乱などしているとアホとよばれかねない。学業成績のアップにとってもっとも非効率な頭の状態が混乱。混乱してテストでいい点はのぞめない。テストでいい点をとるためには混乱したり考えたりするより、ただただ記憶するしかない。
偏差値(文字に対する記憶力)はむやみに高いが、自分の頭で考え判断する能力のない政治家は実に多い。その理由がここにある。偏差値と思考力は直接関係しない。まして決断力とはまったく関係ない。政治家のみならず多くのエリートといわれる人たちが同じ病にかかっている。 そう考えると近現代の社会が混迷するわけがわかる気がする。世界と比べても現場で働く多くの人々のレベルはきわめて高い。しかし問題は上層部。プロ野球の江本孟紀さんではないが「ベンチがアホやから」としかいいようがない。
そうしたなか、絵本はどのような役割を担ってきたのか。絵本は子どもにとって心地良い混乱をもたらしているのか。
絵本を読んでもらって、なにかというと「ああ、それぼく知っている、知っている」という子ども。そうなると身も蓋もない。知ることの快感も大事だが、子どもは混乱からどんどん遠ざかる。知識は増えても自分で考える頭にはならない。早期教育の落とし穴がここにある。なんでもはやければいいわけではない。
多くの絵本はいまだに「ぼく知っている、知っている」という子どもを生みだす方向にある。
その方向を決定づける代表的な考えかたの一つが起承転結。なぜ絵本には起承転結が大事だと考えたのか。
子どもを導きたいとおもっている大人がいる。それも絵本を使って。そんな大人にとって絵本で一番気になるのが結論のあるなし。結論こそが子どもを導く最も重要な到達点であると考えた。すると起承転結の結が勝手に一人で歩きだす。そういう人たちは絵本を読んで絵本に結論がないとダメをだす。そのうえ、ちゃんとした結論がないと子どもは不安になる。そんなことまで言いだす。
不安になることと、結論がなく頭のなかが混乱するのとは別のはなし。不安になると頭はコンクリート化して固まっていく。混乱すると本人がメンドクサくなって逃げださないかぎり頭は活発になる。
しかしメンドクサくて逃げだしてしまう子どもはいくらもいる。なんでもすぐメンドクサがる子どもが絵本を読んで「おもしろいな!」と感じるように表現できるか否か。ここでプロとしての絵本作家の力量が問われる。
どだい子どもを導くのはむり。そうおもって間違いない。ことに絵本で導くなどはなからむり。子どもはそうやすやすと導かれてはくれない。むりなことにぐだぐだ時間をかけるより、作家はすべからくおもしろくて、たのしい絵本をつくるのが先決。絵本を子どもが夢中になって読む。すると、知らず知らずのうちになんらかの影響をうけるもの。導くよりはるかに効果的。
そもそも本当に子どもが不安になる絵本や話に問題があるのだろうか。
では、子どもはどんな時、不安になるかを考えてみよう。子どもは親に依存して生きている。その親がいなくなったり、あるいは親に見放されるのではないか、とおもうと不安になる。迷子になったり、両親の激しい諍(いさか)いを経験すると、いやでも不安になる。
もう一つの不安を昔話や絵本で考えてみる。怖い昔話は、言ってみるとマッチポンプのようなもの。自分で火をつけて自分で消す。大人は怖がらせておいて、「いやぁ大丈夫、大丈夫。よしよし、おじいちゃんがついているからね」などと言いながら怖がらせた本人が子どもをなだめる。子どもが一人で読んだり、見知らぬ赤の他人に怖い話をしてもらうのとではわけがちがう。
話し手である祖父母や親は子どもにとってゆるぎない信頼関係にある。いくら怖がっても「このひとが自分を見捨てるわけがない」という信頼感にゆるぎはない。怖い話でも平気の平左。怖い話を囲炉裏端でも、布団のなかでも、いくらでも聞いていられる。昔話のよさはここにある。大好きなおじいちゃんの話だから、逃げださないで聞いていられる。
怖いけど安心、安心だけど怖い。そういった不思議な混乱がおきる。混乱ゆえに想像もめぐらすことになる。
現実の不安と架空の話や絵本で感じる不安とではまったく別のものである。二つの不安を混同してはいけない。
ここで唐突ですが、長新太さんはエライということになる。五味太郎さん、谷川俊太郎さん、佐々木マキさん、元永定正さんもエライ。これらの作家たちはは起承転結絵本のように「こうなったら、こうなって、最後はこうなんだね」という秩序ある世界にとらわれずに絵本をかいてきた。予定調和とは異なる世界をえがいてきた。これらの作家たちは世界的にみてもはじめてあらわれた特別な絵本作家たちといっていい。
人間社会というものは、そう簡単に割り切れるものではない。余談だが一つの原理でなにごとも割り切れるという考えがあった。それをイデオロギーという。
子どもたちも起承転結ではいいあらわすことのできない世界で生きている。そんな子どもたちも共感できる世界を絵本に描いた。そのトップバッターが長新太さん、五味太郎さん、谷川俊太郎さん、佐々木マキさん、元永定正さんたちということになる。
これらの作家以前と以後とでは絵本の世界はまったく違うものになった。
それ以前の絵本は起承転結、予定調和の時代。それ以後の絵本は省略と混乱の時代となった。省略と混乱の絵本では、子どももじっとはしていられない。省略と混乱となると子どもの頭は自然と動きださざるをえない。
起承転結を気にしなくなると、絵本の展開は一気にひろがる。起もなく。起もないのだから承もない。もちろん結もない。あるのはただ、転のみ。
そうなると絵本はいきなりはじまり、いきなり終わることもできる。だから、ことわりもなく「ごろごろにゃ―ん」であったり、「もこもこもこ」であったり、「のでのでので」「け」となったりする。
赤塚不二夫さんではないが、「なんでもあり!」ということになった。
絵本の未来は正月でもないのに、一陽来福、気宇広大、前途洋洋といった気分になる。実にめでたいかぎりではないか。そうおもっているのはわたしだけだろうか。