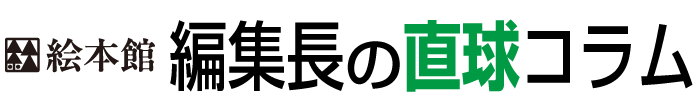ぜひ学校でやってほしいことがある。国語の授業で、教材は『走れメロス』でもなんでもいい。読んだあと先生が「この中に嘘が3つあります。それはどこでしょう」という授業をやってほしい。
どうしてかというとオレオレ詐欺。オレオレ詐欺が流行っている。ということは疑うことを知らない人がたくさんいるということ。学校では疑うことは御法度。「疑いのすすめ」という教材は見たことがない。反対に疑いの心をもって他人に接するのは罪悪だと教え込まれてきた。
そうなると学校にまかせてはいられない。長い人生、詐欺から身を守るためにも自力でやるしかない。詐欺まがいの人間は仕事関係でも恋愛に関しても周りにいくらもいる。
なに簡単です。ちょっと疑ってみる。それを習慣にすればいい。疑うという言葉がきつければ、ものごとをちがう角度から見る力、と言い直してもいい。
原子力発電も基本は詐欺。原子力発電の広告宣伝費に年間883億。1日にすると2億4千万。詐欺性がなければ、こんなに膨大な広告宣伝費を使うわけがない。テレビも新聞、雑誌もみんな心棒が溶けおちてしまった。電気代という金にたっぷり漬け込んだら今のようなマスコミができあがった。
そんな宣伝費のためにみんなで電気代を払ってきた。ほとほとあきれた仕掛けと言うしかない。その上交付金等の名目で年約4000億の税金が投入されている。
同じ公益独占事業のガス、水道が年間どれほどの広告費を使っているか。調べれば電気事業の詐欺力がハッキリする。
新聞、放送といった報道機関だけでなく、われわれ出版ももとをただせば単なるおせっかい。ただ問題は「おせっかいなんだ」という自覚を持った大人がどれだけいるかということ。問われているのは「おせっかい」の質。
子どもに「おしえて」と頼まれてもいないのに、「ねえ、ねえ」と子どもをつかまえて「実はこうなんだよ」なんて言う。そんなことが好きな大人。「おせっかい」にもほどがある。品がいいかわるいか、かなりあやしい。
ところが品位に関係なくほとんどの人は表現したいとか、目立ちたいという欲がある。それも人間だから、けっしてわるいわけではない。
たとえは悪いが、表現とは排泄のようなもの。人間五感で取りいれたものを自分なりの形にして出す。排泄する。それが表現。人間はそんな生き物。
絵本は28ページ、32ページと形式としては短い。短いにもかかわらず、いや短いがゆえに読み手の想像力がふくらむ。そこが重要。読み手の大人や子どもにとって、そこに絵本の実力と醍醐味がある。
ところが現実は説明的な絵本がほとんど。絵は文章の説明。結果なにもふくらまない。ただただ何かを伝えたり、教えたり。すると伝えたいと思っている範囲内でしか読み手のおもいは広がらない。想像する必要がなくなる。
わかるには二つある。ひとつは数学の計算のように整然と「わかる」というもの。もうひとつは、感情が力になって「わかる」という気になるもの。だから主人公に感情移入しすぎると思い込みや誤解、錯覚におちいりやすい。
『走れメロス』をほとんどの人はメロスの立場で読む。メロスの心の動きに共感しながら読む。それをメロスの友人セリヌンティウスの立場で、またメロスの妹の立場で読みなおせば、ちがった気持ちがわいてくる。見方をかえると心はちがったおもいがうまれる。多様な見方を持てば世界が広がる。
人はあるものがたりに共感する。「なるほど」という確信をもつ。すると知らず知らずのうちにそれが自分の信条になっていく。メロスの立場にたてば、正義感と信念、それにあつい友情。ところが友人や妹から見ると、メロスは直情径行、思慮分別に欠ける単なるオッチョコチョイ。メロスの立場だけでみていると『走れメロス』は人を単細胞化させる。ものがたりは人をだます。そんな力をもっている。
物事を判断するとき、感情はなるべく横においたほうがいい。ところが日常生活で感情を横におくのはなかなかむつかしい。
そのむつかしい状態で判断すると「絶対だ」という思いにかられる。頭は感情におおわれてしまう。なにかにつけ人間「絶対だ」とおもうと、ろくなことを考えない。
好きなひとが言った言葉は「なるほど」とすぐ納得する。嫌なやつが言えば、いきなり「そうとは思いません」という垣根が立ち上がる。考えると人間なかなか厄介な生きものだ。
人間客観の上に立つのは至難のわざ。感情が個人的に男女ふたりの間で起こっているのならいい。それは恋愛。
ところが社会とか国とか民族とか、そういうレベルになると大変。オサマ・ビン・ラディンとブッシュ。あれはまさしく感情込みの判断。そして行動。だからあんなにすごいことになった。怒りや興奮が感情を支配すると判断力はとんでもない方向にいく。ここぞというとき一番冷静にならなければならない人、それが政治家であってほしいのに現実は逆。
人はすぐ感情で動く。すると簡単に勧善懲悪ゾーンに入る。民も「そうだ、そうだ、やれやれ」とはやしたてる。後戻りしたいとおもっても、凡百の政治家は今さら間違いだとは言えない。
そう考えると、気づいたらすぐ「まちがい、まちがい」と言える大人はすごい。新聞やテレビでも間違えたときこそが勝負といえる。間違えた報道をしたとき、間違えた記事と同じ量だけ後日の紙面を白紙にする。そうすると恥ずかしい。しかし新聞社は「ごめんなさい」を明確にすることができる。
すると、子どもたちは「大人でも間違えたら謝るんだ」ということを知ることになる。子どもだけでなく大人にも大きな影響をあたえる。社会の風通しは格段によくなる。ここに光がさせばわれわれの社会もすてたものではなくなる。
間違いは報道だけではない。われわれの世界にもある。「しっかりしたストーリーがないと子どもは不安になる」とか、「子どもには起承転結が必要だ」と言う人がいる。思い込みにもほどがある。子どもを見ていないにもほどがある。子どもはうまれたそばから、身の回りのものすべてがどういう因果関係にあるのかわかっていない。因果律という世界にはいない。因果律がわからないと不安になる赤ちゃんや子どもがいたら、会ってみたい。
ひるがえって考えると、因果律の世界に足をふみいれると大人に近づいたということなのか。
「しっかりしたストーリー」や「起承転結」の対極にあるのがナンセンス。多くの大人は「これはなんなのだ」とおもう。たとえば長新太作『ごろごろにゃーん』(福音館刊)。なぜはじめからおわりまでずっと「ごろごろにゃーん」なのか。ほかにいいようがないのか、と大人はおもう。しかし子どもは、まったく困らない。精神がやわらかく、頭も活発に動いているのが子ども。だから子どもとナンセンスの相性はいい。
よくわからないけど気にしない。流れがある。リズムがある。子どもは感じる力が強いからそれでいい。わかる、わからないより大事なのはリズム。全体の流れ。ちがう言い方をすれば直感。ナンセンスは直感を鍛える。
絵本は短い形式だから、読み手の想像力がふくらむためには、因果律でつながっていないほうがいい。美術家の横尾忠則さんがイギリスの著名な演出家フランク・ハウザー『演出についての覚え書き』の書評にこんな文章をよせている。観客というところを子どもと読みかえてお読みいただきたい。
演出家ハウザー氏は「観客(子ども)には常に推測をさせよ。」「ユーモアの最大の理解者は観客(子ども)だ。」という。
そしてこの書評の最後に横尾さんは「著者ハウザーも『すべての点をつないではいけない』と言う。物はバラバラに存在して自他の区別のない方が、観客(子ども)もより想像的になるのではないだろうか」と。
すべてを因果でつないではいけない。バラバラがいい。すると子どもはより想像的になる。まるでナンセンス絵本のための言葉ではないか。はじまりも、終わりも、もちろん途中もいきなりでいい。絵本にはそれができる。絵本の魅力もここにある。
物理の世界でも分子がつながっていない状態ほど物質は活発に動く。個体と液体と気体を比較すればよくわかる。分子が固まっていない気体が一番活発に動く。人も同じ。精神が固まると頭は動かない。
子どもの想像力を心配するより、心配すべきは子どもより大人ではないか。ことに新聞、放送、出版の人たちが疑う力、ちがう角度から見る力を鍛える必要がある。それには生活にユーモアとナンセンスを取り入れるといい。
ところが現実は反対。
作家の丸谷才一さんは
日本の国語教育には、遊び心を大事にする部分はありません。恐ろしく、しかもくだらなくまじめです。(中略)きちんとしかもおもしろく自分の論旨を展開できる技術、つまり論理的表現能力を問うべきだと思っています。
(文芸春秋2008年6月号『「KY」が日本語なんて…』より)
ことに「おもしろく」のところに赤い線を引きたい。
まじめをほめたたえて安心しているようでは、明日の社会に光はささない。
もうすこし体も心もゆるめるといい。