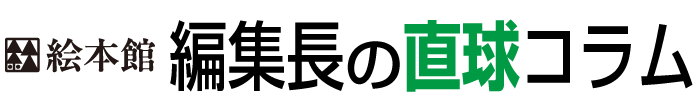毎週日曜、楽しみにしている新聞の書評があります。
毎日新聞の書評です。著名な書評子と読みごたえある内容。おすすめです。
犬との散歩の途中、駅のキヨスクに行って買ってきます。阪神が勝った日はディリースポーツも買います。
家に帰ってコーヒーでも飲みながら読む。けっこう至福の時間です。
先日文楽の人形遣いで人間国宝の吉田文雀さんのインタビューがのっていました。
『文楽のかしら』(国立文楽劇場)という本を監修した方です。
現在文楽のほとんどの首(かしら)を制作している大江巳之助さんの仕事について吉田さんが述べた部分があります。
大江さんがえらいのは首(かしら)の表情をとことんまで突き詰めて彫っていないところです。その一歩手前で引いている。これは出来ないことです
と。
とことんまで突き詰めない、一歩手前で引いている。その結果、人形遣いが舞台で表現できる余地が残されている
のだそうです。
これを読んだ時、絵本とまったく同じだと思いました。
文楽を絵本にたとえれば首(かしら)の作者の大江さんが絵本作家、人形遣いの文雀さんが読者である大人や子供です。
どこが文楽と絵本が同じか。一部を置き換えてみます。
すぐれた絵本作家がえらいのは絵本の文や絵をとことんまで突き詰めてえがいていないところです。
その一歩手前で引いている。これは出来ないことです。その結果、読者が絵本のなかで想像できる余地が残されている
ことになる。
文楽の首(かしら)の作者と同じように、すぐれた絵本作者も一歩手前で引きます。
一歩手前で引くことで余白、隙間がうまれる。
省略や飛躍になります。省略や飛躍があるから読者に想像が生まれる。
俳句のことを思い起こしてみればわれわれ日本人はすぐに合点がいくでしょう。
絵本は俳句に似ています。
ただなんでも絵や文に省略や飛躍があればいいというものではありません。
一歩手前で引く。
にもかかわらず見る者に不自然な印象や違和感を与えない。
この域に達するとプロもプロ、達人の境地です。
絵本の絵には絵本の絵なりの流儀があります。
一枚の絵でなにもかも画こうとする絵画(タブロー)とはおのずから異なるスタイルがあります。なにもかも画いてしまっては絵本の絵にはなりません。十数枚の絵が積み重なるのですから一枚一枚の絵に省略や飛躍が施されているのはあたりまえです。
たとえば五味太郎さんの『おばさんのごちそう』。
とびらのページにはドアだけが描かれています。まわりの壁はありません。しかしおばさんの家だとわかります。
同じく『でんわでおはなし』では、額と絵だけが描いてあります。それだけで室内だとわかる。
描かれていない部分を読み手が想像して、その絵を完成させるもよし、しなくてもなんの問題もありません。自由です。
ほのめかすような象徴的な表現方法です。
言葉でこの方法をもちいたのが俳句です。
絵本の文にも絵本の文なりの流儀があります。絵本の文章は小説家が目指す文章(散文)とは異なる文章のスタイルをもっています。
散文は文だけでその場の情景や風景、あるいは登場人物の心の動きを描ききらねばなりません。
このような小説家志望の人が書くような文章は絵本の文章にむきません。
理由ははっきりしています。
背景も状況もとことんまで突き詰めて描いた文章でできた絵本。そういった絵本の文章は読むだけで情景や風景が思いうかぶ。すると絵はいらないことになります。このような文章を使ったのでは絵本にはなりません。
そこで散文とは異なる絵本ならではの文章を考えてみましょう。
たとえば誰かに絵本を読んでもらう。あなたは目でもつぶってただ聞くだけ。
するとなんのことだかさっぱり分らない。チンプンカンプン。散文の文章精神とは対極にある文章です。
五味太郎さんや長新太さんなどの絵本の文はこれです。
たとえば『おまたせしました・2』。
全ページ文章は「おまたせしました」だけです。絵を見ずに文だけ聞いたらチンプンカンプンです。ところが絵を見ながら文章を聞いていると、なんの違和感もありません。
散文とは異なる絵本の文章です。
このように絵本の絵は絵画から見れば不完全。絵本の文は散文的文章論からすれば論外。
ところがその不完全な絵と論外である文を瞬時に合成しているのは読者のわれわれです。
このような合成力を駆使して絵本を読んでいるわれわれ読者もすこしはクリエイターです。
自然に(知らず知らずに)大人や子供が想像し思い描く絵本。読者もクリエイティブな状態になっている。
わたしはここに絵本の醍醐味があると考えています。
そんな力をもっている絵本。そうした表現を心がけている作家。
絵本作家がこうした表現を心がけているか、いないか。絵本の表現に大きな差が生まれます。
なにより絵本表現が出だしのところで大きく二手に分かれると考えても不思議ではありません。
言い換えれば、この差は子供をどう観るかということでもあります。
子供が生まれた時は白紙の状態、早くからなにかと教え導かねばならないと考えるか。
それともそれぞれの子供はすでにある種の感性や感受性をもった、いっぱしの人間として生まれてきている。
もちろん言語をふくめた表現の方法は未だ至らずの状態。
ただ子供たちが大人と普通に接していれば言語も常識もいずれ自然と身につくと考えるか。つまりあせるか、あるいは気楽に考えるか。いずれの子供観、生命観のうえに大人が立つか。それによって子供のおかれる環境におおきな差が出てくるのではないでしょうか。
また大人になるということはこの生まれながらに持っていた感性や感受性をすこしずつ失う、あるいは見失うことなのかもしれません。
すぐれた絵本作家は「大人になんかなってやらないからな」という、子供の感性や感受性をもったままのめずらしい大人なのかもしれません。
以前、五味太郎さんが
自分が絵本をつくる。それを奥さんに見せる。するとおもしろがる。それで今度は出版社の人間に見せる。するとまたおもしろがる。そうすれば全国に何千人か、おもしろがる大人や子供はいるはずだ。
それくらい絵本の出版は気楽に考えたほうがいい
と。
この気楽さがいい。
なぜか。それぞれの子供の個性を結果として尊重している考え方だからです。
それとはまったく逆の考え方があります。
「絵本は子供の目線でつくらなければならない。保育園や幼稚園の子供たちをよく観察しよう」という考え方。
子供たちを観察する。子供は動物や植物ではないのです。
親にとって子供は学問や科学の対象ではありません。
子供を観察しないと絵本がよく分らないと考えている人間は絵本に関係しないほうがいい、とわたしはおもっています。
子供一人一人のこと、まして人間の心の動きなど観察したってそう簡単に分りっこありません。
熱心に観察すればするほど子供のことや心のうごきがよく分る。これは近代がもたらした妄念です。自分のことでも分らないことはいくらもあります。
ところが母親はつい自分が大変な思いをして生んだ子だし、毎日一緒にすごしているし、なにより思い入れはひとしおだし、といろいろおもいが積み重なって、子供のことならたいていのことは分っている、あるいは分らねばならない。そう考えがちです。
いましがたお会いしてきた谷川俊太郎さんが
本当のストレスは本人にも分らない。分っているストレスは本当のストレスではない
と。
事ほど左様に人の心はいまだに分らないことがおおいのです。
子供のことでも分った気になりすぎると、親の精神は硬直してコンクリート化してしまうのではないでしょうか。
子供もあたりまえですが人間です。
人間のことだから分らないこともあると高をくくるぐらいの気持でいたほうがいいバランスではないでしょうか。
親にとっても子供にとってもさっぱりとすがすがしい毎日になります。請け合います。
そういった気持で子供と接していると絵本の楽しみも広がります。これもまちがいありません。
ダブルで請け合いましょう。