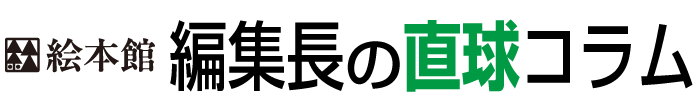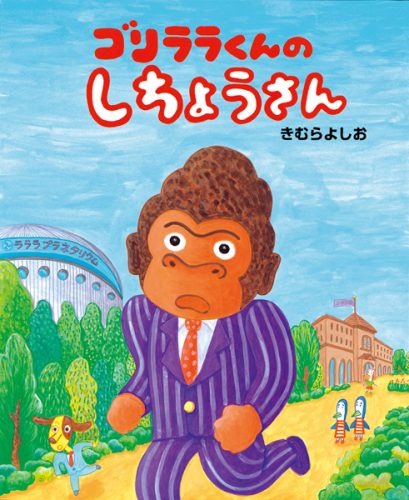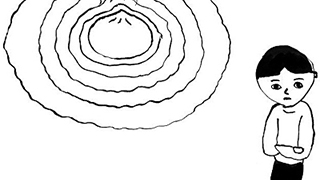知ってるかな、車のハンドルにはクリアランスというものがある。止まっている車のハンドルを持つと少し動く。つまりハンドルにはゆとりというか余裕がある。
一般的には「ハンドルのあそび」といっている。そのあそびの機能がないと事故になる。ハンドルにあそびがあるから車は真直ぐ走る。遊園地のゴーカートのような車が街を走ったら大変。事故だらけ。あそびは車にとってなくてはならないものだ。
人間の精神も車と同じ。あそびがないと大変なことになる。なにより生活がギスギスする。本人もまわりもつまらない。人間らしく暮らすためにも心にあそびはなくてはならない。自分の生活のためにも他人との関係においても、あそびは必要不可欠。
気むずかしくて、仏頂面の人がいるギスギスした家庭や会社。考えただけでぞっとする。あそびやユーモアが、子どもというか人の一生にどれほど資するか、はかりしれないものがある。
平安時代『梁塵秘抄』の昔から「遊びをせんとや生れけむ」と日本では言ってきた。明治以降、日本は伝統から乖離(かいり)しすぎた。もうすこし日本人も伝統を重んじたほうがいいのではないか。
俳画というものがある。芭蕉も画いたそうだが、代表者、完成者は与謝蕪村。
ほろにがい人生の悲しみ、心のそこからわきでる感情、それをおもてだっては表現しない日本人の感性、その境地を蕪村は俳画の世界で表現するようになった。
その俳画に「ベタづけ」と「匂いづけ」という言葉がある。
蕪村以前の俳画は、絵と句のつながり方が直接的だった。そういうベタづけをきらって蕪村は匂いづけという俳画を完成させた。絵と句をはなして、そこをやわらかく連想でつなげるようにしている。蕪村の俳画は絵と句が響きあう。そういうやわらかい構造になっている。見る人が読みとるたのしさ。見る人が参加していく参加型のジャンル。省略のきいた絵で句の意味とつかずはなれずあらわされている。
この長い引用は学習院大学小林忠先生の俳画についての言葉です。
「古池や かわずとびこむ 水のおと」の芭蕉の句に、水にとびこむカエルを描けば、これはベタづけ。
蕪村の「學問は 尻からぬける ほたるかな」には文机に向かい中空をあおぎみながら筆をもてあそぶ男が描かれている。これが蕪村の俳画、匂いづけ。
小林先生の言葉は俳画だけのものではない、絵本の核心もいいあてている。テレビでこの言葉を知ったときのわたしの状態を四字熟語であらわせば欣喜雀躍、ひらたく言えば大よろこび。
「なんだ、絵本は欧米伝来とおもっていたけれど日本のお家芸だったのか」です。
今おこなわれている絵本はほとんどがベタづけ。ベタづけ絵本をつくる大人たちは、子どもはわからないことが多い。だから説明してあげねばと思う。そんなおせっかいな、というか野暮な大人がつくる絵本がベタづけ絵本。なにごとも絵解き、説明だから子どももおもしろいわけがない。見る人、つまり子どもにとっても読みとるたのしさがない。
匂いづけ絵本では「おもしろい」が第一。まず子どもが感覚的、直感的におもしろいと感じなければ本にたいする親しみはわいてこない。
小林先生の言葉を絵本にいいかえると、匂いづけ絵本は「絵と文をはなしてそこをやわらかく連想でつなげるようにしている。絵と文が響きあう、そういうやわらかい構造。見る人が参加していく参加型の絵本。省略のきいた絵で文の意味とつかずはなれずあらわされている」。それを「見ている子どもが読みとる楽しさ」。そこに絵本のおもしろさ、醍醐味がある。
このような心の動きは絵本だけにかぎったことではない。絵でも音楽でも文でも、あるジャンルの芸術をおもしろいとおもう。その心の動き。そこには読みとるたのしさ、参加するたのしさがある。そのたのしさを感ずるようになれば、そのジャンルの芸術と自分が親しいあいだがらになったも同然です。趣味の誕生はそんな瞬間にある。
趣味がめばえる。すると、あそびの心もそだつ。
ここまでは読者の側のはなし。
つぎは創る側、作者。作者にとってなにが重要か。なにより作家が絵本を創ること、それ自体がおもしろくなければ、はなしにならない。作家のおもしろいとおもう心、そういった作者の創作意欲をつつがなく発揮できるよう、環境をととのえる。それがわれわれ出版社、編集者のいちばんの仕事です。
ここでまた匂いづけのはなしにもどります。
この匂いづけ絵本の作者は長新太、五味太郎をはじめ日本には有力な作家が何人もいます。そこに今、きむらよしおという新星があらわれた。『ゴリララくんのコックさん』という絵本には、きむらよしお的なあそびがちりばめられている。その広大なあそびのフィールドのかなたにちくわの穴とちくわという虚と実がうかびあがる。
『ゴリララくんのコックさん』に続く『ゴリララくんのしちょうさん』は、更に「虚と実」「匂いづけ」が色濃く躍動している。虚と実といっても笑いのなかの虚と実ですよ。
そのうえ、このゴリララくんは世のオヤジの手本にもなっている。「オヤジができることは、ただみまもるだけ」。そんな父親にとって肝に銘じなくてはならない至言を現わしている。
きむらさんの『ねこガム』(福音館書店)には、この虚・実、そして笑いが簡潔にそして端的にあらわれている。「あれ、これってなんだったんだろう」
と、キツネにつままれたような気持ちになる。そんな読後感がまたいい。そこに絵本のたのしさがある。
ゴリララくんシリーズとは別に、2010年2月発売の『はしれ、はしれ』という絵本に至っては「疾走する虚空」と言いたくなるほどの世界が描かれてい
る。あるいは「虚空のなかの哀愁」かな。哀愁といっても、ものがなしい悲しみのなかにあるユーモアです。
すべてのベースにあるのが愛嬌とユーモア。そこにきむらよしお絵本の魅力がある。
ほんとうにすばらしい。
こんな絵本は今までなかった。
絵本もここまできたか、という気持になれてうれしい。こうした絵本を多くの子どもたちが楽しんでくれると、ことのほかではあるのだが。
日本は鳥羽僧正『鳥獣戯画』のような絵本的表現を700年前からやってきた。その上、江戸時代の南画、俳画、草双紙の伝統の上にいま現在の絵本は立っている。世界的にみても日本の絵本が非常に高いところにある訳です。
そう考えると長新太、五味太郎など匂いづけ的な絵本作家たちは与謝蕪村の嫡流(ちゃくりゅう)、直弟子にあたるのかもしれない。
最後にぼくのすきな蕪村の句を一つ。
「涼しさや 鐘をはなるる かねの声」